どうも、Flare大橋です。
最近、なにかと話題の「AIエージェント」。なんだか面白そうだし、業務も効率化できるかも?なんて軽い気持ちで、自分でも作ってみようと安易にやりはじめました。THEミーハーです。
結果、
AIに丸投げで、魔法のように賢いツールがサクッと出来上がるなんてことは、夢のまた夢でした。
結局のところ、それを使う人間の「頭脳」、つまり思考力が一番大事なんだなと、身に沁みてわかりました。今日はそんな私の七転八倒の格闘記です。
格闘の末に見えてきた、AIを使いこなすのに本当に必要なこと
いやー、本当に色々ありましたよ。無限に吐き出されるエラーの数々。Geminiに「これで最後です!絶対にエラーはでません!」と言われ信じて突き進んで同じエラー吐いたり。。。
AIと真剣に付き合い始めてまだ2週間ですが、私なりの試行錯誤の末に、「AIをまともに使うには、これがないと絶対にダメだ」というポイントが見えてきました。
1. 生成AIの「クセ」をちゃんとわかってないとダメ
まずこれ。ひとくちに「生成AI」と言っても、付き合い方で全然違うんですね。
例えば、普段私たちがチャット画面でGeminiと対話しながら何かを作るのと、APIという仕組みを通じてAIに自動でタスクを処理させるのとでは、全くの別物です。
対話なら「ちょっと違うな」と思ったらその場で指示を修正できますが、API経由だと、一度決めた指示を淡々とこなすだけ。最初は「そんくらいAIがよしなにやってくれるっしょ!」なんて思ってたんですが、AIは「よしなに」とか「いい感じに」が一番苦手。
彼らの特性、つまり「得意なこと」と「できないこと」を理解してあげないと、スタートラインにすら立てないと思い知らされました。
2. ノーコードでも「開発的な思考」は必須だった
「ノーコードツールだから開発知識ゼロでいけるんじゃね?」なんて淡い期待を持っていた2週間前の自分をぶん殴りたい。
もちろんプログラミング言語を書く必要はないんですが、論理的に物事を考える「開発的な思考」がないと、まったく話になりませんでした。
特に痛感したのが**「マッピング」**という概念。
「このステップで出力されたこのデータを、次のステップのこの部分に使う」といった、データの流れを正確に紐づけてあげないと、AIエージェントはまったく動いてくれません。「そんなの自動で理解してよ!」って最初は思いましたけど、無理でした(笑)。
AIはあくまで指示された通りにしか動けない、超真面目だけど応用が利かない部下みたいなもんなんです。
3. 「業務の切り分け」ができないと、ただのトンチンカンなAIが爆誕する
そして何より、これが一番のキモかもしれません。
「そもそも、何のためにこのAIエージェントを作るんだっけ?」「どの業務をやらせたいんだっけ?」という目的が曖昧なまま作ると、ただただ複雑で使いにくい、トンチンカンな代物が出来上がります。
やらせたい業務フロー全体をきちんと想像して、「ここからここまではAIに」「この判断は人間が」と正しく切り分けて、的確に指示を出す。
これって、システム開発における「要件定義」そのものですよね。
この設計が独りよがりだと、まさに「指示が下手な駄目上司に使われる、可哀想な部下(AI)」みたいな構図が出来上がってしまいます。
4. 相談相手のAIがドツボにハマったら、最後は自分の頭で
開発の過程では、もちろんGeminiやGPTに相談しながら進めるわけですが、彼らも万能ではありません。
たまに一緒にドツボにハマって、トンチンカンな回答をループし始めることがあるんです。本当に(笑)。
そんな時、AIの提案を鵜呑みにして「AIが言うなら…」と突き進むと、永遠に沼から抜け出せません。「いや、ちょっと待てよ」と立ち止まり、最終的に自分の頭で考えて軌道修正する力が絶対に必要です。
開発的な思考までAIに丸投げして、自分では理解する気がないと、いつの間にかAIの分析に振り回されるだけになってしまいます。
まとめ:結局、AIに「何をさせるか」を考える思考力を鍛えないと始まらない
今回のAIエージェント作成への挑戦でわかったのは、AIはめちゃくちゃ優秀な“道具”や“部下”ではあるけれど、決して魔法の杖ではないということ。
そして、その優秀な道具を使いこなすには、結局、指示を出す「人間」のスキルが問われるんだなと痛感しました。
何を、何のために、どうやってやらせるか。
この「設計思想」こそが、これからのAI時代に一番価値を持つスキルなのかもしれません。AIエージェント作りは、自分の思考力を鍛える最高のトレーニングでした。
いやー、大変だったけど面白かった!
体調不良で寝込む夫の看病もせずに一生朝から晩までPCカタカタしてしまった。反省。(過集中が過ぎる泣)

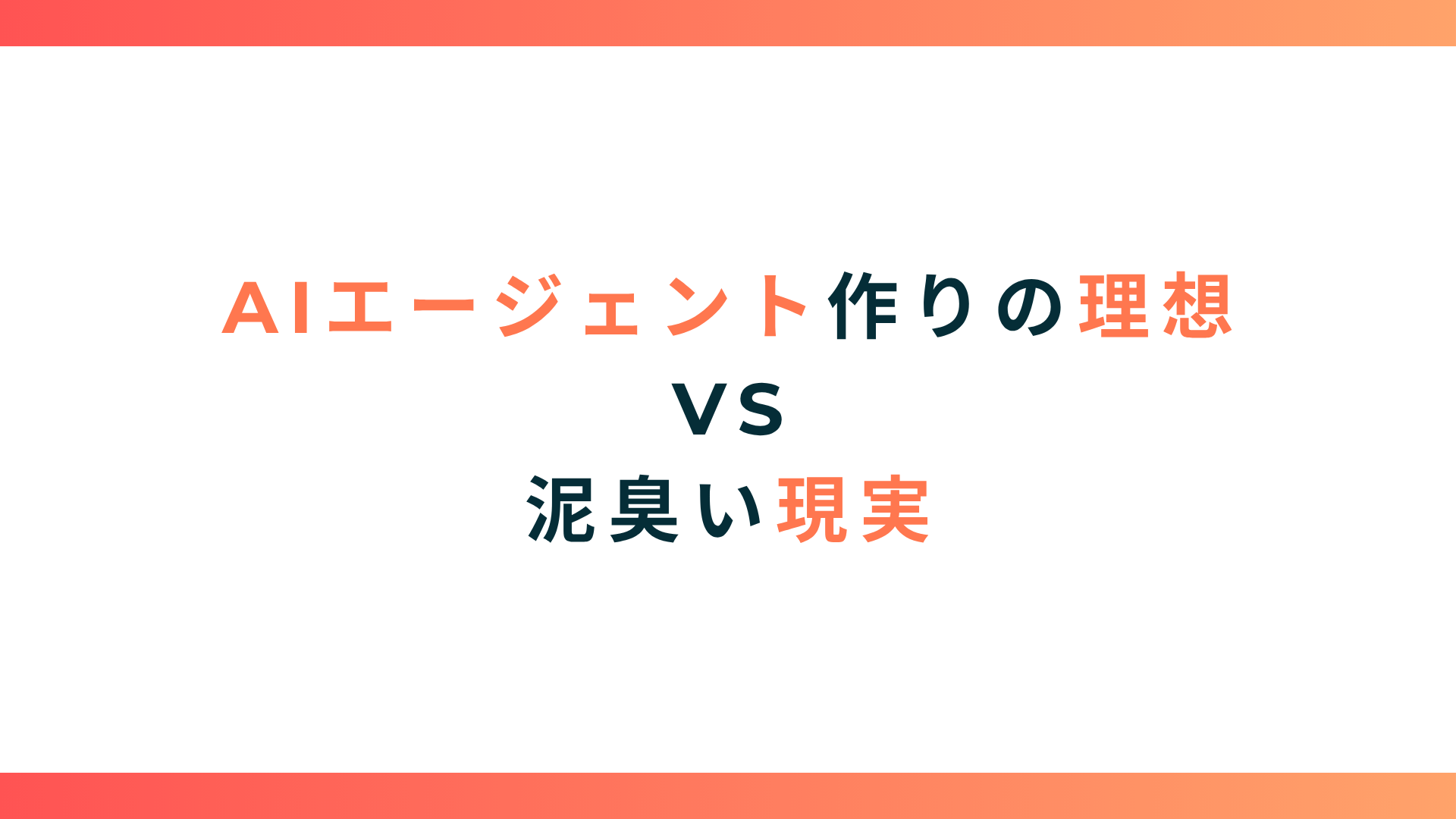
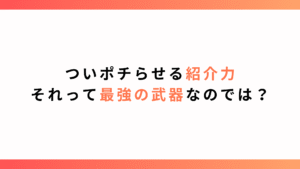
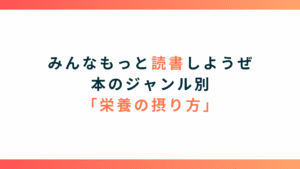
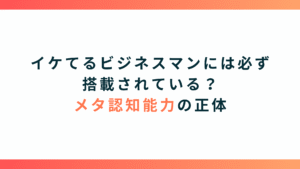
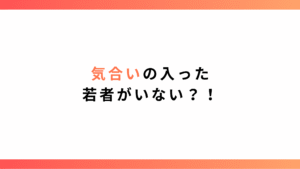
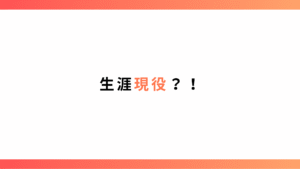

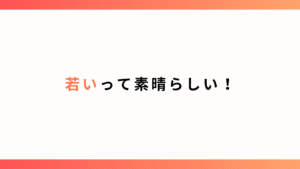
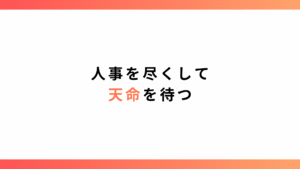
コメント