時々、「大橋さんはよく本を読みますよね。私にはとても真似できません」「昔より本を読むことに抵抗ができてしまって…」という声を聞くことがあります。
確かに私は大体1日ビジネス書1冊(読まない日もある)、常時小説は持ち歩いていて、漫画もいっぱい読みます。
ですが、何を隠そう、私も読書歴が長いわけではありません。習慣としてよく本を読むようになったのは、ここ半年くらいのことです。
なのでこの記事では、元々“本の虫”ではなかった私の、現在の読書ルーティンについて書いてみようと思います。読書が苦手な方にも、何かヒントがあるかもしれません。
そして、いきなりですが、私は本を「ちゃんと」読んでいません。
ビジネス書は1日1冊ペースで朝の1時間で速読。かと思えば、小説は移動時間に数週間かけてのんびり味わう。そして漫画は、一度ハマると4時間ぶっ通しで没頭する。
要するに、本のジャンルによって、読み方や期待値をガラッと変えているんです。
今日はそんな私の、一見メチャクチャだけど意外と理にかなってる(と自分では思っている)読書習慣と、本の「栄養の摂り方」についてお話しします。
ビジネス書は「集合知」を得るためのすっ飛ばしナナメ読み
私にとってビジネス書を読む目的は、書かれているノウハウを100%暗記することではありません。
Amazon Unlimitedなどを活用して、例えば「起業」とテーマを決めたら関連本を片っ端から読み漁ります。良書もあれば、正直イマイチな本も混じっていますが、それでいい。
大事なのは、たくさんの本に書いてある**「共通項」**を見つけ出すこと。個別の知識は9割忘れてしまっても、複数の著者から抽出された共通項が頭の中に残れば、それで大成功だと考えています。
1日1冊、朝1時間の「斜め読み」ルーティン
私は毎朝犬の散歩をし、朝ご飯を食べ、いつも8時ごろに出かける夫を見送ってから仕事を始めるまでの1時間、ちょっとゆるっとした時間があります。そのざっくり浮いた1時間でビジネス書を1冊読み終える、というのを日課にしています。
もちろん、精読なんて到底できません。わからない部分があっても、気にせず飛ばしてしまいます。 ここでは、とにかくスピードと数を重視。たくさんのページをめくることで、その分野の全体像がぼんやりと地図のように見えてくる感覚を大切にしています。
狙いはアイデアの化学反応
Aという本とBという本、それぞれ主張が違うことも多々あります。 ですが、乱読していると「あ、Aのこの部分と、Bのこの考え方は繋がるな」という瞬間がふと訪れます。
この、複数のアイデアが頭の中で混ざり合って起きる化学反応こそ、ビジネス書の乱読による成果と捉えています。私のビジネス書への期待値はこんなもんです。1冊をじっくり読んでバイブルにする、みたいな激高期待値をもってたら疲れちゃう。
小説・漫画は「知らない世界」のお散歩
一方で、小説や漫画は完全に効率度外視。「寄り道」を楽しむ散歩のように読みます。
基本的にはのんびり電車移動の時間とかで読んでいますが、少し前に読んだ古典『氷点』、あれは凄かったなぁ。本当に本から私に向かって手が伸びてきて、胸ぐらを掴んで引きずり込まれるような、そんな感覚で没頭して読んでしまいました。
自分とはまったく違う人生を追体験し、その世界の景色や空気感を想像する。この時間が、ロジックで凝り固まった頭を柔らかくほぐしてくれるんです。
「ビジネス書だけ」では悲しい
これは完全に私の持論ですが、周りのビジネスマン達の間では、ビジネス書ばかりが結構読まれているのが少し寂しい。
小説がくれるのは、正解のない世界で揺れ動く人の心への理解です。
人の気持ちの機微がわからないと、結局のところビジネスだって上手くいかないのではないでしょうか。個人的な感覚ですが、小説をよく読む人の方が、共感力が高く、優しい人が多い気がします。
あと、小説を読めるって、贅沢ですよ。読めばわかる。
さいごに、皆さんに伝えたいのは、読書って結構期待値低くて良いんじゃない?ということです。
先に書いたビジネス書なんて、ザクザクテキトーに読んじゃえば良いんです。小説は面白かったら読み進めればいいし、面白くなかったら途中でやめちゃえば良い。
私なりの読書との向き合い方、スタイルが何かのお役に立てれば、と思います。
ではまた。

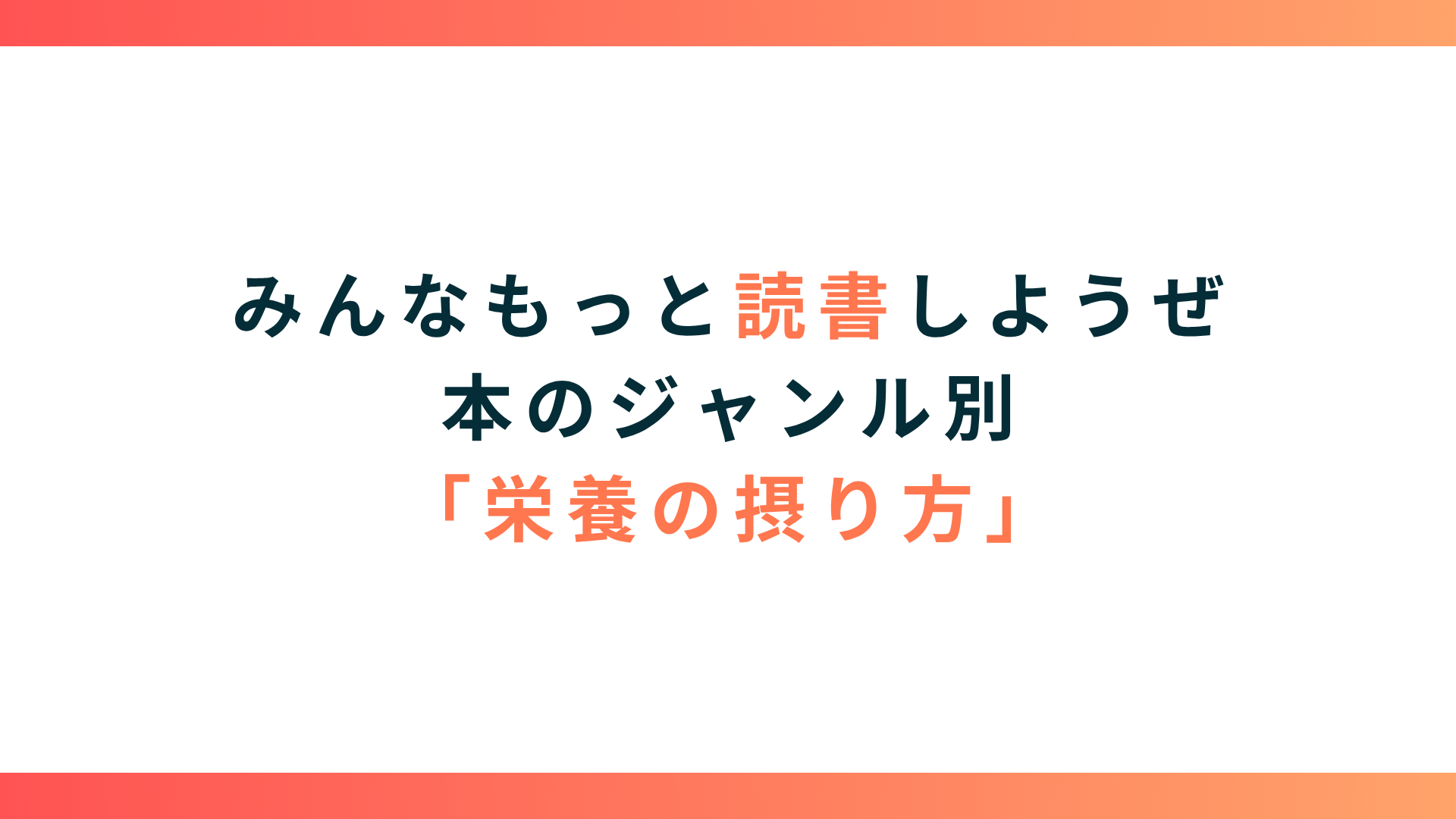
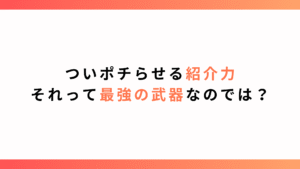
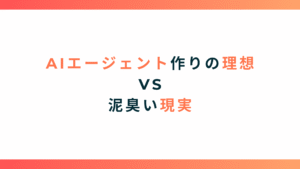
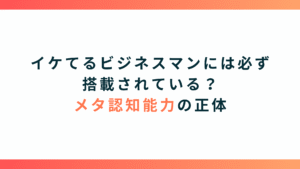
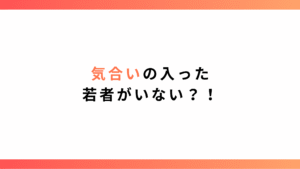
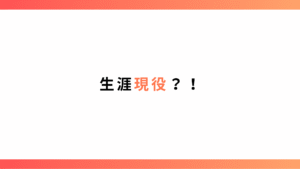

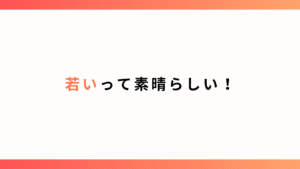
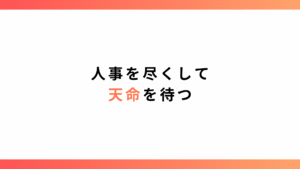
コメント